※本記事にはプロモーション(PR)が含まれています。
※本記事の画像・引用は作品紹介のために使用しています。著作権は著作者・出版社に帰属します。
作品のレビューについて
本記事では、早良朋『へんなものみっけ!』をレビューしつつ、博物館(ミュージアム)の価値と、学芸員・研究者と地域社会がつくる知の循環について考察します。ネタバレは避け、作品の魅力と“学びの面白さ”を伝えます。
基本情報
- タイトル:『へんなものみっけ!』
- 作者:早良朋(さわら とも)
- 出版社:小学館
- 掲載誌:週刊ビッグコミックスピリッツ
- ジャンル:博物館×日常ドラマ×教養漫画
- 巻数:既刊12巻(連載中)
- その他:博物館を舞台に、学芸員や研究者、地域社会との関わりを描いた異色の作品。
あらすじ

舞台は地方都市にある「市立博物館」。新米学芸員として赴任してきた主人公・臼井徹が、動物学や考古学、民俗学などさまざまな分野の「へんなもの」と出会い、学芸員や研究者たちと一緒に奮闘する姿を描きます。
「博物館」と聞くと堅苦しいイメージを持つ人も多いですが、本作では日常の出来事と学芸員の仕事をユーモラスかつ丁寧に紹介。展示物の裏にある学問的な背景や、地域の人々の暮らしと密接に結びついた歴史・文化の断片が描かれていきます。
例えば、動物の骨やフンの採集・調査や標本作成、地域伝承の調査、地域住民との交流などもストーリーに登場。「へんなもの」とは単なる珍品ではなく、そこから広がる動物たちの営みや学びを指しています。主人公と仲間たちは、日常の中で学びと発見を重ねながら成長していくのです。
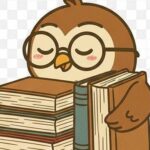
大事なものは残していく。
色んな人や動物との出会いが人を成長させる。
キャラクターの魅力
本作は主人公を含め、多彩で個性的なキャラクターが織りなす群像劇が魅力です。
- 臼井徹
博物館に新しく配属された若手学芸員26歳。最初は知識も経験も不足しているが、ひたむきさと好奇心で「へんなもの」に向き合っていく。読者と同じ目線で博物館や研究の世界を体験する案内役的存在。 - キヨス先生
動物大好きな研究者。ひと際大きなツバメの神様を探してこの研究が始まった。
ちょっと変わっているけれど、この物語の中で皆を引っ張っていく存在。
キヨス先生の信念に徹は突き動かされていく。 - ベテラン学芸員たち
動物学担当、考古学担当、民俗学担当など、それぞれの専門分野を極めた人物が登場。彼らの深い知識と研究熱心な姿勢はコミカルでありながら尊敬を誘う。 - 地域の人々
博物館と地域社会をつなぐ存在。昔から伝わる道具や言い伝えを持ち込み、学芸員との交流を通じて「モノ」に新しい意味が見出されていく。
キャラクターの一人ひとりが専門分野の情熱を持ち、時にぶつかり合い、時に協力し合う。その姿は「研究者ってこんなに面白い!」と読者に伝えてくれるのです。

働く人の一生懸命な姿は美しい。
人も動物も一緒だね。
生き物と“知”を未来へ手渡す

① 博物館の役割は「収集・保存・研究・展示・教育普及」
資料を集め、守り、調べ、それをわかりやすく伝える。加えて、地域活性・多世代交流・学習機会の創出など、社会と共創する場としての役割も持っています。
② 「へんなもの」は珍品ではなく“問いの入口”
骨・糞・道具・伝承──どれも学びの扉。一見些細なものが、生態・歴史・文化へとつながる。臼井たちは「モノの背後にある物語」を可視化していく。
③ 保存は“命の継続”を可視化する技術
保存がなければ多くの生物資料は時間とともに失われる。適切な処置・管理によって、未来の研究や教育の資源が確保される。標本の前に立つと、生き物の営みが今も続いているように感じられる瞬間がある。
※寄贈手続き・記録(ラベリング)・保存環境など、現場の地道な実務が価値の持続を支えている点も見逃せない。
絵柄と雰囲気
絵柄はリアルさと柔らかさのバランスが絶妙です。学術的な部分は丁寧に描かれ、化石や標本などもリアリティを持って表現されています。一方でキャラクターの表情や動きはユーモラスで、読みやすく親しみやすい雰囲気。
また、博物館の静謐な空気や発掘現場の荒々しい風景など、シーンごとの雰囲気が豊かに表現されており、空気感まで伝わってきます。
雰囲気全体としては「知的好奇心をくすぐる穏やかな日常系漫画」でありながら、「研究者の情熱と苦労」をリアルに感じさせる硬派さも備えています。
印象に残ったシーン
臼井徹がカモシカの毛皮をなめした後、「人の記憶にほとんど残らない僕が、100年後の未来に残るものを作ったのか」と自分の仕事を噛みしめるシーン。本人は市役所で無駄を省くことが得意でやってきたが、新たな価値観に出会った瞬間です。価値のあるものを世に残すという仕事を通してみる新たな視点は読者の中でも刺さる人はあるのではないでしょうか?
どんな仕事も大変で必要なものですが、なんとなく成果に結びついていないなどありますよね。そんな時に一度立ち止まってみるきっかけになるかもしれません。
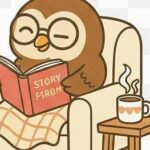
新しい価値観に出会えた時。人は成長する。
きっと誰にでもどんなタイミングかは分からないけどそんな時が訪れる。
こんな人におすすめ
- 博物館や歴史、考古学、動物学に興味がある人
- 『もやしもん』や『銀の匙』のような教養×エンタメ作品が好きな人
- 日常の中で知的な刺激を求めたい人
- 学芸員や研究者の仕事に興味がある学生
- 穏やかな物語を楽しみながら知識を得たい大人
類似作品
- 『もやしもん』(石川雅之):微生物をテーマに学問とユーモアを融合。
- 『銀の匙 Silver Spoon』(荒川弘):農業高校を舞台に、日常と学びを両立させた作品。
- 『天地明察』(漫画版):学問と人間ドラマを描いた歴史科学漫画。
- 『チ。-地球の運動について-』(魚豊):学問への情熱と社会との葛藤をテーマにした名作。
Q&A

Q:博物館に行ったことがなくても楽しめる?
A:はい。むしろ博物館初心者こそ「こんな裏側があったんだ!」と驚きが多い作品です。
Q:専門知識がないと難しい?
A:作中でわかりやすく説明されているので安心して読めます。
Q:教育用に使える?
A:学校や図書館でも推奨されることがあるほど、教育的価値の高い作品です。
まとめ
『へんなものみっけ!』は、博物館を舞台にした稀有な漫画であり、学芸員や研究者の日常をユーモラスかつ感動的に描いた作品です。
「へんなもの」とは、単なる珍品ではなく、歴史や文化、人の営みそのもの。その視点を漫画として表現することで、博物館や学問を身近に感じさせてくれます。
読後には「博物館に行きたい」「もっと学びたい」という気持ちが自然と湧いてくるはずです。知的好奇心を刺激されたい人には、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

動物たちと真剣に向き合う姿はカッコいいね。
生き物の中で私たちも生きていることを伝えてくれる良い作品だった。
全体を通しての感想
ただただ、生き物として生きること。その生きてきた証を保管し、その価値を紡ぐこと。小さな営みの数々を保つために一生懸命に奮闘する博物館のスタッフに感動する作品です。命の尊さを感じて毎日に感謝して生きていけそうです。
購入リンク
本を手に取って生き物たちと博物館のスタッフの奮闘を見に行こう!
購入リンクは下記から。
作者の他作品
作者の他作品は現在のところありません。(2026/1現在)
関連記事
生き物や働く人たちについての記事も書いてます。
ぜひ読んでいってください👇
▶関連記事:「BEASTARS(ビースターズ)」──肉食と草食と複雑な恋心
.jpg)







コメント