※本記事にはプロモーション(PR)が含まれています。
基本情報
『さよなら絵梨』は、『チェンソーマン』『ルックバック』『ファイアパンチ』などで知られる藤本タツキ先生が2022年に「少年ジャンプ+」で公開した読切漫画です。公開直後から大きな話題となり、SNSを中心に「衝撃作」として一気に拡散されました。
ページ数は約200ページに及び、読切としては非常に大ボリューム。単行本化もされ、ファンからは「藤本タツキ作品の中でも特に深い余韻を残す一作」として高く評価されています。
あらすじ
物語は、主人公の少年・優太が母親から「自分の死ぬまでの映像を撮り続けてほしい」と頼まれる場面から始まります。優太はその願いに応え、母が病で亡くなるまでの過程をカメラに収め続けました。しかし、母の死後に上映した映像は周囲から酷評され、優太は深い挫折を味わいます。
そんな彼の前に現れたのが、謎めいた少女・絵梨。彼女は映画好きで、優太に「一緒に映画を撮ろう」と提案します。二人は日常を映しながら関係を深めていきますが、やがて絵梨にも秘密があることが明らかになり……。
現実と虚構、愛と死、創作と記録。映画のように繰り返される映像の演出を通じて、読者は「生きるとは何か」「残すとは何か」を問いかけられる物語です。
キャラクターの魅力
優太
母の死を撮り続けたことから始まり、人生を「映像」と共に歩むことになる主人公。素直で未熟ながらも、撮影という行為を通して現実と向き合い、成長していきます。
絵梨
映画好きな謎の少女。明るく、どこか超然とした雰囲気を持っていますが、その存在には秘密が隠されています。彼女が優太に与える影響は計り知れず、物語の核心に迫る存在です。
優太の母
死を目前にしても「映像に残してほしい」と願う母の姿は、物語の始まりに大きなインパクトを与えます。彼女の依頼が、すべての出来事を引き起こすきっかけとなります。
絵柄と雰囲気
『さよなら絵梨』の絵柄は、藤本タツキ作品らしいラフさと大胆なコマ割りが特徴です。特に映画のスクリーンを模したようなコマ配置は、読者に「映像を観ている感覚」を与えます。
雰囲気としては、日常的な会話の軽さと、死や別れをめぐる重さが共存しており、そのコントラストが強烈な余韻を生み出しています。また、ユーモアとシリアスが交互に訪れることで、読者は「これは現実なのか、それとも映画なのか」と揺さぶられる体験を味わうことになります。
印象に残ったシーン
- 母の最期を映像に残す場面
冒頭から強烈な印象を与えるシーンであり、「死を映す」というタブーに挑んだ藤本先生らしさが表れています。 - 爆発の演出
物語の節目で「建物が爆発する」という荒唐無稽な演出が繰り返されることで、現実と虚構の境界が曖昧になります。この手法は賛否両論を呼びましたが、藤本作品ならではの挑戦的な仕掛けです。 - 絵梨の秘密が明かされる場面
読者の予想を裏切り、衝撃と切なさを同時に与えるシーン。物語全体のトーンを決定づけています。
こんな人におすすめ
- 心に刺さる「読後の余韻」を求める方
- 普通の漫画では味わえない、映像的な表現に惹かれる方
- 生と死、愛と記録というテーマに関心のある方
- 『ルックバック』『チェンソーマン』など藤本作品を読んで心を揺さぶられた方
- 実験的な構成やメタ的な物語が好きな読者
類似作品
- ルックバック(藤本タツキ):友情と創作、そして喪失を描いた感動的な読切。
- チェンソーマン(藤本タツキ):血と暴力の中で「普通の生活」を夢見るデンジの物語。死と生のテーマが共通。
- ぼくらの(鬼頭莫宏):子供たちが「死」と向き合うSF作品。重いテーマと独特の余韻が近い。
- 聲の形(大今良時):人との関わりや後悔を描く作品。現実と感情の交差が似たテーマを持っています。
Q&A
Q1:『さよなら絵梨』は難しい作品?
A1:映画的な構成や爆発の演出が独特で、最初は戸惑うかもしれません。ただ、読み進めるうちに「現実と虚構の境界」を考えさせられる奥深さがあります。
Q2:泣ける?
A2:はい。特に母の死や絵梨の秘密に触れる場面は涙を誘います。ただし、感動と同時に虚無感や不思議な余韻も残る作品です。
Q3:どこで読める?
A3:少年ジャンプ+で公開された後、単行本化されています。電子書籍(Kindleなど)でも読むことが可能です。
まとめ
『さよなら絵梨』は、映像と現実をめぐる独特の物語であり、読者に強烈な問いを投げかける作品です。母の死を撮影するというショッキングな導入から、絵梨との交流、そして衝撃のラストまで、まるで一本の映画を観ているかのような読書体験を味わえます。
藤本タツキ先生らしい挑戦的な構成とテーマ性が詰まっており、『ルックバック』と並んで「作家の力量を最も感じられる読切」として評価される理由も納得です。
読後の余韻を味わいたい方、創作や記録の意味を考えたい方にとって、必ず心に残る一冊となるでしょう。
.jpg)
.jpg)
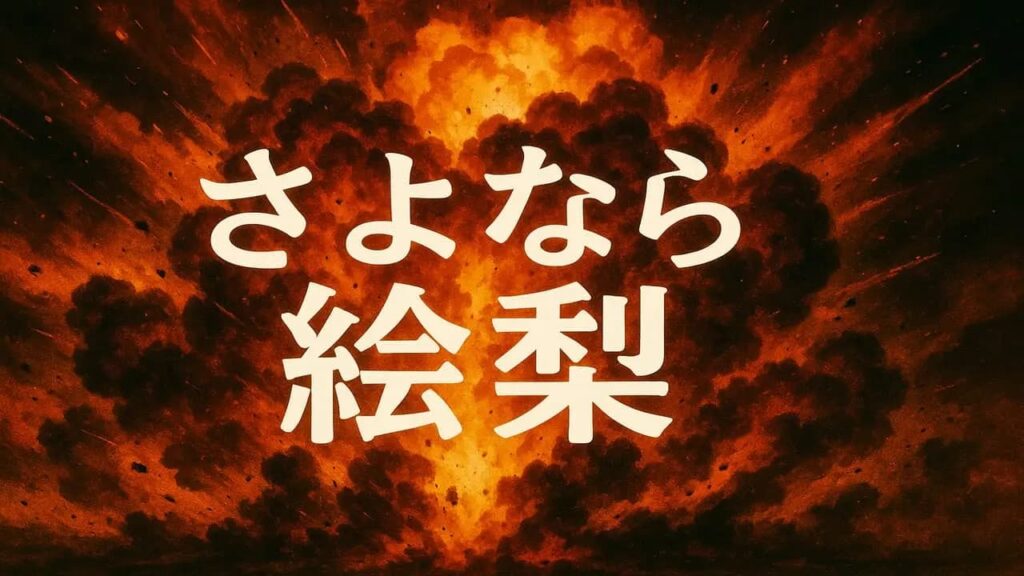


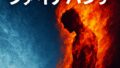
コメント